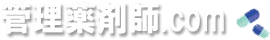抗凝固薬(DOAC等)一覧と使い方
| 分類 | 成分名 | 商品名 | 規格・剤形・補足 |
|---|---|---|---|
| クマリン系 | ワルファリンK | ワーファリン | 規格:顆粒0.2%、錠0.5mg/1mg/5mg、錠2㎎と細粒0.2%はGEのみ 適応:血栓塞栓症(静脈血栓症、心筋梗塞症、肺塞栓症、脳塞栓症、緩徐に進行する脳血栓症等)の治療及び予防 |
| 抗トロンビン | アルガトロバン | ノバスタンHI スロンノンHI |
規格:注 適応:長いので略 |
| DOAC(直接的トロンビン拮抗薬) | ダビガトラン | プラザキサ | 規格:カプセル75mg/110mg 適応:非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 |
| DOAC(直接的Xa阻害薬) | リバーロキサバン | イグザレルト | 規格:細粒分包10㎎/15mg/包、錠10mg/15mg、OD錠10㎎/15mg、DS51.7mg/103.4㎎ 適応:【成人】非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制、静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制、【小児】静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制、Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制 |
| エドキサバン | リクシアナ | 規格:錠15mg/30mg/60mg、OD錠15mg/30mg/60mg 適応:非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制、静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制、(膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術)の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制 |
|
| アピキサバン | エリキュース | 規格:錠2.5mg/5mg 適応:非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制 |
|
| 合成Xa阻害薬 | フォンダバリヌクス | アリクストラ | 規格:皮下注 適応:静脈血栓塞栓症の発現リスクの高い、(下肢整形外科手術施行患者、腹部手術施行患者)静脈血栓塞栓症の発症抑制 |
| ヘパリン関連 | ヘパリンNa | ヘパリンナトリウム ヘパフラッシュ |
規格:注 適応:静脈内留置ルート内の血液凝固の防止 |
| ダルテパリン | フラグミン | 規格:静注 | |
| ヘパリンCa | ヘパリンカルシウム | 規格:注、皮下注 適応:血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析)、汎発性血管内血液凝固症(DIC) |
|
| パルナパリン | ローヘパ | 規格:透析用 適応:血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析・血液透析ろ過・血液ろ過) |
|
| エノキサパリン | クレキサン | 規格:皮下注 適応: (股関節全置換術、膝関節全置換術、股関節骨折手術)の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制、静脈血栓塞栓症の発症リスクの高い、腹部手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制 5. 効能又は効果に関連する注意 |
|
| ダナパロイド | オルガラン | 規格:静注 適応:汎発性血管内血液凝固症(DIC) |
プラザキサ、イグザレルト、エリキュース、リクシアナと言ったNOAC(non-vitamin K antagonist oral anticoagulants)DOAC(direct oral anticoagulant)と呼ばれる抗凝固薬が続々と発売されて、心原性脳塞栓症という言葉が耳に入る機会が多くなった気がします。
これらの抗凝固薬は、それまでのワーファリンが納豆や青汁といったビタミンKを大量に含む食物を一緒に食べれないことや定期的に血液検査が必要といった煩わしさを淘汰し、期待されて出てきた薬剤です。
そんな矢先にでたプラザキサのブルーレター・・・。これにより、ワーファリンのほうが使いやすいと思ったDrも多いのではないでしょうか。腎代謝80%だから高齢者に使いづらいのが原因で、これがブルーレターの原因となりました。
さて、心原性脳塞栓症とはどういう疾患なのか、ワーファリンやプラザキサ、エリキュース、イグザレルトは抗凝固薬で、パナルジンやプラビックスは抗血小板薬、何が違うのか?
心房細動(AF)とは
心房細動は、弁膜症性心房細動と、非弁膜症性心房細動(NVAF)に分類される。
- 弁膜症性心房細動・・・僧帽弁狭窄症や大動脈弁閉鎖不全症のような弁膜疾患によるもの
- 非弁膜症性心房細動・・・高血圧や糖尿病、心不全、血管疾患、甲状腺機能亢進症、自律神経調節異常などを背景とするもの
無秩序に起こる心房の興奮(400~600/min)を原因として起こる心房細動では、まず左心房の拡大による息切れ、上室性期外収縮が引き起こされ、ついで左室の拡大が起こる。BMPも100~200へ上昇する。この際、淀んだ血液が左心耳に滞留し、血栓が形成されてこれが脳に関わらず、いろいろな場所へ行き塞栓症を引き起こす。
心房細動では動悸やめまい、胸痛等の自覚症状が乏しいため、通常、心電図検査を行うか、携帯型ホルター心電図を装着して24時間モニタリングすることで発見されることとなる。
左心房の拡大とその症状は血圧のコントロールにより下げることが可能。
基本の治療は、まず脈を下げる(レートコントロール)。
これにはジギタリス、Ca拮抗薬、β遮断薬が使用される。ジギタリスは動作時の脈は抑えにくいので心不全合併例に?、血圧が低い場合はCa拮抗薬のヘルベッサーやワソラン、血圧が高い場合はメインテートやアーチストがしばしば用いられる。
次に生活習慣病の合併症(DMや高血圧、甲状腺機能亢進症etc...)を取り除く。
その後、腎機能が問題なければDOACを使用(初めからDOACを使用しない。腎機能が悪ければワーファリン)。そして再度レートコントロール。状態により抗不整脈薬を加えたり、貧血を伴うCKD等でOAC服用が好ましくない(出血リスクが高い)時はアブレーションを行う。
ただし、CKD合併例においてはアブレーション後の再発率がきわめて高いため、アブレーションやOACに変わる治療としてLAAC(左心耳閉鎖術)という左心耳を網目のある風船みたいなもので封鎖して塞栓ができるのを防ぐ治療法が出てきて96%以上の結果(OACの中止)を叩き出している。
CHADS2スコアとHAS-BLEDスコア
DOACを使用する場合は、CHADS2スコア(心不全:Congestive heart failure、高血圧:Hypertensiton、75歳以上の高齢者:Age、糖尿病:Diabetes mellius、脳梗塞、TIAの既往:Stroke/TIA)を用いて薬剤を選択する。
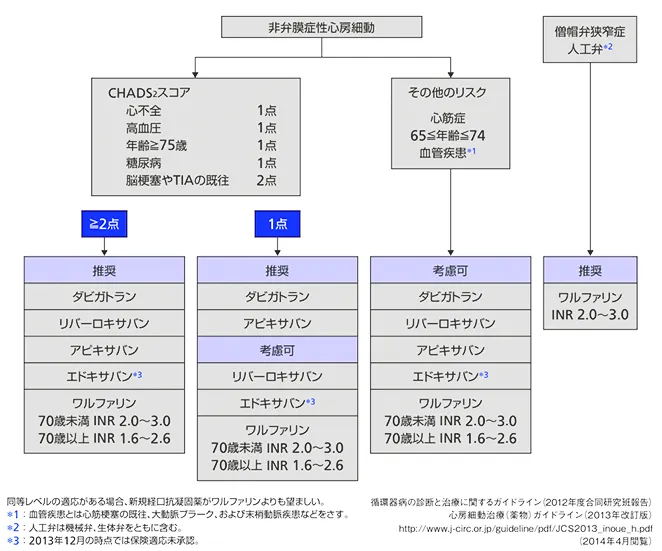
同スコア1点に考慮可のリバーロキサバンやエドキサバンは未試験という理由なだけで効果が劣るというわけではない。また、DOACが推奨されるのはNVAFだけであり、弁膜症性心房細動にはワーファリンが推奨されている。
ヨーロッパではもっと詳しいCHA2DS2-VAScが使用されるが、日本ではめんどいという理由でガイドラインでは採用されていない。CHA2DS2-VAScには0点もあるのでより詳しく判定するために用いられたりする。
出血しやすい人はHAS-BLEDスコアを用いる。
各抗凝固薬(DOAC)の特徴
各DOACの特徴が以下。
| プラザキサ プリズバインド |
イグザレルト | エリキュース | リクシアナ | |
|---|---|---|---|---|
| 標的因子 | トロンビン | 第Xa因子 | 第Xa因子 | 第Xa因子 |
| T1/2(時間) | 12~14 | 9~13 | 8~15 | 6~11 |
| Tmax(時間) | 0.5~2 | 2~4 | 1~4 | 1~1.5 |
| BA | 6.5%(人) | 67~86%(動物) | 49%(人) | 60%(動物) |
| 蛋白結合率 | 35% | 92~95% | 87% | 40~59% |
| 代謝 | グルクロン酸抱合 | CYP3A4/2J2 | CYP3A4 | CYP3A4 |
| 腎排泄 | 80% | 33% | 25% | 35~39% |
| プロドラッグ | ○ | × | × | × |
DOACはワーファリンに比べて脳出血のリスクは低いものの、消化管出血のリスクが高い。ガイドラインではDOAC使用患者に対するPPI併用は推奨となっている。
胃潰瘍の既往があったり、便潜血が認められる場合はPPI併用が望ましいものの、出血は下部消化管の場合もあることや適応の問題でPPIの全ての患者への予防投与については賛否両論ある。
- 心房細動は全てのタイプの認知症を増やす。
- DOACはワーファリンより出血はもちろんのこと、認知症も減らす。
- イグザレルトとプラザキサは高齢者で出血リスクが高くなるデータ有り
- 心房細動の80歳以上の有病率は6.1%
- やせは心不全再入院に関係する。AFと低体重は心不全の生命予後を悪化する。低体重は脳卒中のリスクだが出血は変わらず。
- 年齢、脳卒中の既往とバイオマーカー(NT-proBNP、Troponins、GDF-15)、CKDが脳卒中を予測する
- AFは加齢、心疾患、動脈硬化指標、CKDと関係する
- フレイルは低体重とCKDと関係し、心房細動の死亡率を増加する。
- CKDでeGFR60以下や心不全では心房細動を合併しやすい
- 85歳以上はCHARsスコアと相談しつつ、本人の意向で出血リスクと相談して続けるかどうかを決める。
ワーファリン
ワーファリンはビタミンKに拮抗することで、上で出てきた四つの血液凝固因子(Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ因子:水色の文字)を抑制してしまうため、Ⅶ因子阻害による頭蓋内出血のリスク(脳内にTFが多いため)や他の凝固因子阻害による他の出血のリスクも高めてしまいます。
プロテインCやプロテインSといった凝固抑制因子も阻害してしまう。
そのため、ワーファリンでは、プロトロンビン時間という血液が固まるまでの時間と、それを指数化したPT-INRを用いて、大体1.6~3.0(通常は2.0前後)に調整することで出血リスクを管理します。
ワーファリンは投与5日目くらいまでは血栓ができやすいのと、ビタミンKで中和後、もとに戻すのに1週間はかかる。
納豆、青汁、クロレラの同時摂取はワーファリンの作用を減弱させるので禁忌。市販の整腸剤に含まれる糖化菌の一つ、納豆菌も禁忌。
プラザキサ
プラザキサは直接的トロンビン拮抗薬として、Ⅱa因子(トロンビン)と、トロンビン-TM複合体を阻害する。
メリットは、ワーファリンと違ってビタミンKに拮抗するわけではないので、納豆や青野菜といった食事の制限を受けないこと、頭蓋内や消化管出血のリスクを減らせるということ、PSやPC等のVK依存性の凝固抑制物質を阻害しないことが挙げられる。
デメリットは、生体内に恒常的に存在するトロンビンをも抑制するため、出血リスクが上がることや、トロンビン-TM複合体への親和性のほうが強いために活性化PCの合成を阻害して抗凝固が妨げられること、トロンビンは血小板リン脂質上に存在するXa因子に比して分子自由度が高いため、活性を阻害すると腎排泄が高まるので腎機能障害患者に使いにくい。実際、イグザレルトやエリキュースの腎排泄率が30%前後であるのに対して、プラザキサの腎排泄率は80%である。
比較的メジャーな抗真菌薬イトラコナゾールと併用禁忌である。
吸湿性が高く、アルミピロー包装から出した状態での安定性は3ヶ月、PTPから取り出すと1日持たない。もちろん一包化は不可である。
中等度の腎機能障害、P-糖タンパク質阻害剤の併用、出血リスクの高い患者については減量(110mg)を考慮する。
ワソランとの併用によりプラザキサの血中濃度が上昇することがあるため、プラザキサを服用中にワソランを併用する場合は、併用開始から3日間はワソラン服用の2時間以上前にプラザキサを服用する必要がある(3日間はプラザキサ服用→2時間以上→ワソラン服用)。逆(ワソラン服用中にプラザキサ服用はそのままで併用でOK)。どちらにしても血中濃度を考慮して110mgの使用を考慮すること。
中和剤は、プリズバインド静注液(イダルシズマブ)である。プリズバインドはプラザキサの特異的中和剤。
イグザレルト、エリキュース、リクシアナ
イグザレルトとエリキュース、リクシアナは、Xa因子の活性中心のS1ポケットに直接結合してⅩa活性を阻害する薬。
XaはセリンプロテアーゼドメインとEGFドメインとGlaドメインからなっていて、GlaドメインはビタミンK依存性に活性化され、これがあるCaと結合できると同時に膜のリン脂質と結合できるようになる。
メリットは、常に存在している微量なトロンビンを阻害しないのでプラザキサよりも出血リスクが少ないこと、トロンビンよりも上流かつ外因系と内因系のちょうど交わるところを阻害すると効率が良い(XⅠ因子1分子→Xa因子870分子→トロンビン12万分子→フィブリン2億分子)こと、加えてプラザキサと同様のメリットがある。
デメリットは、同用量であっても個人によって効き方が違うため、用量調整には十分注意する必要が有ること。
- 年齢・・・イグザレルト:75歳以上、エリキュース:80歳以上
- 体重・・・イグザレルト:50kg以下、エリキュース:60kg以下
- 腎機能・・・イグザレルト:クレアチニンクリアランス50ml/min以下、エリキュース:血清Cr1.5mg/dL以上
のいずれか2つを満たす場合は用量を減らして投与することはできるものの、低用量を使用したとしてもリスクは格段に上がるため、このような患者にはワーファリンのほうが分がある。
これら3剤には中和剤がないため、保険適用外であるが、他人の血液を入れるという方法がとられることもある。
リクシアナの用量調整基準(非弁膜症性心房細動、静脈血栓塞栓症)は以下のとおり。
| CLCr(ml/min) | 体重60kg以下 | 体重60kg超 | |
|---|---|---|---|
| P糖蛋白阻害作用を有する薬剤※ | |||
| 併用していない | 併用している | ||
| 50超 | 1日1回30mg | 1日1回60mg | 1日1回30mgに減量(もしくは減量することを考慮) |
| 30以上50以下 | 1日1回30mg | ||
| 15以上30未満 | 投与の適否を慎重に判断 (投与する場合、1日1回30mg) |
||
| 15未満 | 投与不可 | ||
※1日1回30mgに減量(キニジン硫酸塩水和物、ベラパミル塩酸塩、エリスロマイシン、シクロスポリン)、1日1回30mgに減量することを考慮(アジスロマイシン、クラリスロマイシン、イトラコナゾール、ジルチアゼム、アミオダロン、HIVプロテアーゼ阻害薬)
また、出血リスクが高い高齢の患者では、年齢、患者の状態に応じて1日1回15mgに減量できる。(R3.8.27追記)
※リクシアナ60kg以上へのunderdose(30mg使用)はデータがあり、効果はそれなり、出血リスク低い。
イグザレルト(半減期:5~9h)、エリキュース(半減期:12h)、リクシアナ(半減期:4.9h)ともにワーファリン(半減期:55~133h)に比べて半減期が短いため、1日2回の投与が望ましく思えるが、イグザレルトとリクシアナの投与回数は1日1回である。
イグザレルトが1日1回で血中濃度が下がった後の半日間、血液凝固を抑制し続けるメカニズムは以下のようなものである。
- 血管内皮細胞上のTFPIを増加させ(Xaが阻害されるとTFPIがXaに結合できずに温存できるため)、その効果が24時間持続する可能性がある。
- ワーファリンと違ってPSやPCといった凝固抑制因子を阻害しない
- 有効血中濃度でトロンビン生成を強力に阻害するため、ATやトロンボモジュリンなどの消費がなく、温存される
- 上記等の理由で、トラフ濃度でのPT延長が認められなくても、プロトロンビナーゼ複合体を介する凝固時間の延長は持続するため、抗凝固効果が持続している可能性
リクシアナが1日1回で血中濃度が下がった後の半日間、血液凝固を抑制し続けるメカニズムとしては、分布容積が大きいため血液中ではなく組織に大部分が分布しているからとされている。
※分布容積:同じ量の薬剤を投与しても薬剤の種類によって血中濃度は異なるのが普通。同じ量の薬剤を投与したのに血中濃度(薬剤の量/血液量)が高ければ血液の量が少なく、逆に低ければ血液の量が多くないとつじつまが合わないが、人の血液の量が薬剤の種類によって増減するということはなく一定である。ここで言う血液の量が分布容積であり、血液量が一定とすれば容積の増減は組織の容積(組織移行性)の増減によるものと見ることができる。こんなかんじかな?
薬価的にはイグザレルト15mgとエリキュース5mg×2が同じくらい、その1.5倍がリクシアナ60mg→ほぼ同じへ統一。ただし、リクシアナの60mgと30mgの価格がほぼ同じのため、30mgを投与されるべき患者に対して60mgを半分に割って投与することで負担が大分軽減される。
ヘパリン関連薬
ATを介してXaやトロンビンを抑制する薬剤として、ヘパリン、低分子ヘパリン、ダナパロイド、フォンダパリヌクス、アンチトロンビン製剤がある。
ヘパリンは低分子化されるとXa選択性が増し、五単糖の最小単位がフォンダパリヌクスでで最もXa選択性の高いヘパリン関連薬である。
脳梗塞急性期の治療
| 治療法 | 特徴 | 薬剤名 | アテローム | ラクナ | 心原性脳塞栓症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血栓溶解療法 | 発症後4-5時間以内に行う 点滴静注にて血栓を溶解 |
t-PA | ○ | ○ | ○ |
| 局所線溶療法 | 発症後4-5時間以内に行う カテーテルを使って血栓を溶解 |
ウロキナーゼ | ○ | - | ○ |
| 抗凝固療法 | 凝固因子を抑制して血栓を溶解 | ヘパリン アルガトロパン |
○ ○ |
○ - |
○ - |
| 抗血小板療法 | 血小板の抑制して血栓を溶解 | オザグレル アスピリン |
○ - |
○ ○ |
○ ○ |
| 抗浮腫療法 | 頭蓋内圧の上昇を抑制 | 濃グリセリン マンニトール |
○ | - | ○ |
| 脳保護療法 | 活性酸素を抑えて脳組織の壊死を防ぐ | エダラボン | ○ | ○ | ○ |
t-PAは、過去に脳出血既往がある人、脳梗塞の範囲が広い人、抗凝固薬投与中で出血しやすい人、血圧が高い人には使用不可
ワーファリンからイグザレルトやプラザキサへの切り替え
ワーファリン投与時におけるPT-INRの基準値は、70歳未満で2.0~3.0、70歳以上で1.6~2.6が普通であり、この治療域にコントロールされている患者さんの場合、ワーファリン中止後、PT-INRが治療域の下限(PT-INRが70歳未満は2未満、70歳以上は1.6未満になってから)を下回ってから切り替える。
ワーファリンの抗凝固効果は通常、経口投与後48~72h持続するが、個人差が大きいので、PT-INRをモニタリングしながら切り替える必要がある。そうすることで、効果の重複による出血リスクを減らすことが出来る。
逆に、イグザレルト等からワーファリンに戻す場合は、PT-INRが治療域の下限を超えるまでは、両者を併用し、下限を超えたらワーファリン単剤に切り替える。
関連ページ
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No924 題名:Re:AF冠者様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-28 23:15:55
作用点が異なりますので、可です。
アンプラーグの添付文書ではワーファリン患者への投与は慎重投与となっており、出血リスクが高まるので注意はしますが、禁忌ではありません。
記事No922 題名:適合するや否や 投稿者:AF冠者 投稿日:2019-03-28 10:46:15
慢性心房細動でワーファリン1/日服薬中
脊柱管狭窄症でアンプラーグを整形外科で処方された可か不可か
記事No414 題名:リクシアナの低用量 投稿者:テビチ 投稿日:2017-02-16 10:25:03
体重60キロ以上でリクシアナの30mg投与の有効性はみとめられていないですし、そもそも不適切使用で保険適応外です。
記事No387 題名:ダイアライザーの残血 投稿者:まこっち 投稿日:2016-11-25 23:13:21
ダイアライザーにのみ残血があります。
A, Vチャンバーに残血はなし。
バイアスピリンとブラピックス服用していたときは残血がなく、ブラピックスを止めたところ残血が出始めました。。。
APTTは25秒
Fibは400
抗凝固剤は低分子ヘパリンでACTは130
私は低分子ヘパリンではなく、抗トロンビン薬に変更したらと思うのですがいかがでしょうか?
記事No266 題名:Dダイマーと血栓のタイプ別のできる仕組み 投稿者:NEO 投稿日:2016-04-20 21:12:04
お返事、ありがとうございます。
なるほど、おっしゃる通りだと思います。
色々と詳しく教えて頂、ありがとうございました。
- << 前のページ
- 次のページ >>