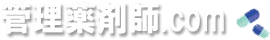パーキンソン病の薬一覧
| 分類 | 成分名 | 商品名 | 規格・剤形・補足 |
|---|---|---|---|
| レボドパ単剤 | レボドパ | ドパストン | 規格:散((985mg/g)/Cap250mg/静注 適応:パーキンソン病、パーキンソン症候群 |
| ドパゾール | 規格:錠200mg 適応:上に同じ |
||
| レボドパ+DCI | レボドパ+カルビドパ | ネオドパストン ドパコール カルコーパ レプリントン |
規格:錠L100mg(レボドパ100mg・カルビドパ10㎎)/錠L250mg(レボドパ250mg・カルビドパ50㎎) 適応:パーキンソン病、パーキンソン症候群 |
| メネシット | 規格:錠100mg(レボドパ100mg・カルビドパ10㎎)/錠250mg(レボドパ250mg・カルビドパ50㎎) 適応:上に同じ |
||
| デュオドーパ | 規格:経腸液(レボドパ2g・カルビドパ500mg) 適応:レボドパ含有製剤を含む既存の薬物療法で十分な効果が得られないパーキンソン病の症状の日内変動(wearing-off現象)の改善 |
||
| レボドパ+カルビドパ+エンタカポン | スタレボ | 規格:錠L50㎎(レボドパ50mg・カルビドパ5㎎・エンタカポン100mg)/錠L100mg(レボドパ100mg・カルビドパ10㎎・エンタカポン100mg) 適応:パーキンソン病[レボドパ・カルビドパ投与において症状の日内変動(wearing-off現象)が認められる場合] |
|
| レボドパ+ベンセラジド | マドパー イーシー・ドパール ネオドパゾール |
規格:錠(レボドパ100mg・ベンセラジド25mg) 適応:パーキンソン病、パーキンソン症候群 |
|
| ドパミン作動薬 (麦角系) |
カベルゴリン | カバサール | 規格:錠0.25mg 適応:パーキンソン病乳汁漏出症、高プロラクチン血性排卵障害、高プロラクチン血性下垂体腺腫(外科的処置を必要としない場合に限る)、産褥性乳汁分泌抑制、【0.25mgのみ】生殖補助医療に伴う卵巣過剰刺激症候群の発症抑制 |
| ブロモクリプチン | パーロデル | 規格:錠2.5mg 適応:末端肥大症、下垂体性巨人症、乳汁漏出症、産褥性乳汁分泌抑制、高プロラクチン血性排卵障害、高プロラクチン血性下垂体腺腫(外科的処置を必要としない場合に限る)、パーキンソン症候群 |
|
| ペルゴリド | ペルマックス | 規格:錠50μg/錠250μg 適応:パーキンソン病 |
|
| ドパミン作動薬 (非麦角系) |
アポモルヒネ | アポカイン | 規格:皮下注30㎎/3mL、投与間隔2h 適応:パーキンソン病におけるオフ症状の改善(レボドパ含有製剤の頻回投与及び他の抗パーキンソン病薬の増量等を行っても十分に効果が得られない場合) |
| ドミン | 製造中止。規格:錠0.4mg、粉砕〇 | ||
| プラミペキソール | ビ・シフロール | 規格:錠0.125mg/0.5mg 適応:パーキンソン病、中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群(下肢静止不能症候群) |
|
| ミラペックスLA | 規格:徐放錠0.375mg、粉砕× 適応:パーキンソン病 |
||
| ロピニロール | レキップ レキップCR |
規格:錠0.25mg/1㎎/2㎎/徐放錠2mg、普通錠粉砕〇、徐放錠粉砕× 適応:パーキンソン病 |
|
| ロチゴチン | ニュープロ | 規格:パッチ2.25mg、肩、上腕、腹部、臀部、大腿へ24hで貼替 適応:パーキンソン病、【2.25mg、4.5mgのみ】中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群 |
|
| ドパミン遊離促進薬 | アマンタジン | シンメトレル | 規格:細粒10%/錠50㎎/100mg 適応:パーキンソン症候群、脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善、A型インフルエンザウイルス感染症 |
| ドパミン代謝賦活薬 | ゾニサミド | トレリーフ | 規格:錠2.5mg/OD錠25mg/50mg、粉砕〇 適応:パーキンソン病(レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合)、 レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム(レボドパ含有製剤を使用してもパーキンソニズムが残存する場合)、 【OD錠50mgのみ】パーキンソン病(レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合) |
| MAO-B阻害薬 | セレギリン | エフピー | 規格:錠2.5mg(GE)/OD錠2.5mg 適応:パーキンソン病(レボドパ含有製剤を併用する場合 |
| ラサギリン | アジレクト | 規格:錠0.5mg/1mg 適応:パーキンソン病 |
|
| サフィナミド | エクフィナ | 規格:錠50mg 適応:レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるwearing off現象の改善 |
|
| NE前駆物質 | ドロキシドパ | ドプス | 規格:細粒20%/OD錠100mg/200mg 適応:パーキンソン病(Yahr重症度ステージⅢ)におけるすくみ足、たちくらみの改善、起立性低血圧、失神、たちくらみの改善(シャイドレーガー症候群、家族性アミロイドポリニューロパチー)、 起立性低血圧を伴う血液透析患者におけるめまい・ふらつき・たちくらみ、倦怠感、脱力感の改善 |
| COMT阻害薬 | エンタカポン | コムタン | 規格:錠100mg 適応:レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩との併用によるパーキンソン病における症状の日内変動(wearing-off現象)の改善 |
| オピカポン | オンジェンティス | 規格:錠25mg 適応:レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩との併用によるパーキンソン病における症状の日内変動(wearing-off現象)の改善 |
|
| アデノシンA2拮抗薬 | イストラデフィリン | ノウリアスト | 規格:錠20㎎、粉砕× 適応:レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるウェアリングオフ現象の改善 |
| 抗コリン薬 | トリヘキシフェニジル | アーテン | 規格:散1%/錠2㎎ 適応:特発性パーキンソニズム、その他のパーキンソニズム(脳炎後、動脈硬化性)、向精神薬投与によるパーキンソニズム・ジスキネジア(遅発性を除く)・アカシジア |
| ビペリデン | アキネトン | 規格:細粒1%/錠1㎎/注0.5% 適応:特発性パーキンソニズム、その他のパーキンソニズム(脳炎後、動脈硬化性、中毒性)、向精神薬投与によるパーキンソニズム・ジスキネジア(遅発性を除く)・アカシジア |
|
| ピロヘプチン | トリモール | 規格:細粒2%/錠2㎎ 適応:パーキンソン症候群 |
|
| マザチコール | ペントナ | 規格:散1%/錠4㎎ 適応:向精神薬投与によるパーキンソン症候群 |
コリンエステラーゼ阻害薬はアセチルコリンを増やすのでパーキンソン病を悪化させる可能性があるが、認知症のパーキンソン病患者に投与は可能、適応もある。
レボドパ含有製剤
レボドパは、ドパミン前駆物質(L-ドパ)、脳内でドパミンに転換されて生理作用を発揮する。
レボドパは、十二指腸を含む小腸上部より吸収され、LAT1/2(アミノ酸トランスポーター、L輸送システム)が吸収に関与している。
レボドパの吸収速度は胃排出時間、胃液のpHなどの影響を受ける。具体的には胃pHが低い方が吸収が高く効果も高い。そのため、合併症として頻度の高い便秘の治療に酸化マグネシウムを使用するとレボドパの効果が減弱するため、他の便秘薬が推奨される。
カルビドパやベンセラジドはレボドパ脱炭酸酵素阻害薬であり、末梢でレボドパが脱炭酸されてドパミンになるのを抑え、レボドパの脳内への移行を高める。
同じレボドパ量だと、レボドパ脱炭酸酵素阻害薬の種類の違いでマドパーの方がメネシットよりも血中濃度が高くなるため、同用量での切り替え時にマドパー→メネシットだとレボドパの血中濃度が下がってしまいます。
- ドパストン、ドパゾール
、ドパール(レボドパ) - ネオドパストン、メネシット、カルコーパ、ドパコール、パーキストン、レプリントン、デュオドーパ(レボドパ・カルビドパ(10:1))
- マドパー、イーシードパール、ネオドパゾール(レボドパ・ベンセラジド(4:1))
レボドパ賦活薬
ドパミン合成を増やし、ドパの効果を強くする。振戦やウェアリングオフ現象を改善する。
- トレリーフ(ゾニサミド) ・・・エクセグランにはパーキンソン病の適応はないので使用不可。
MAO-B阻害薬
選択的MAO-B阻害薬で、モノアミン酸化酵素Bにより代謝されるドパミンの分解を抑えて、L-ドパの作用を長時間維持させる。薬効時間を長くできるため、ジスキネジアには用いず、ウェアリングオフの症状の改善に使用する。
- エフピー(セレギリン)
- アジレクト(ラサギリン)
- エクフィナ(サフィナミド)
COMT阻害薬
選択的COMT阻害薬で、L-ドパの作用を長時間維持させる。ウェアリングオフの症状を改善する。
- コムタン(エンタカポン)
D2受容体刺激薬
ドパミン受容体を刺激してアセチルコリンによるパーキンソニズムを抑える薬。プロラクチンを低下させるため、妊娠、産婦の人は注意する。ジスキネジアを改善する。
- パーロデル(ブロモクリプチン)
- ペルマックス(ペルゴリド)
- カバサール(カベルゴリン)
- ドミン(タリペキソール)
- ビ・シフロール、ミラペックスLA(プラミペキソール水和物)・・・レストレスレッグス症候群にも適応、警告:前兆のない突発的睡眠及び傾眠で自動車事故の危険性
- レキップ、レキップCR(ロピニロール)
- ニュープロ(ロチゴチン) ・・・パッチ剤。D1~D5までに高いアゴニスト活性。レストレスレッグス症候群にも適応。4.5mg/日からはじめ、1週間ごとに4.5mgずつ増量し維持量(9mg~36mg/日)を定める。AED使用時ははがすこと。
- ハルロピ(ロピニロール) ・・・パッチ剤。D2、D3及びD4受容体に親和性及び内活性を示し、ドパミンD1及びD5受容体には親和性を示さない。
- アポカイン(アポモルヒネ)・・・オフ症状レスキュー用の自己注射。最短10分~20分で効果を発現し効果時間約1時間。
DA遊離促進薬
ドパミンの放出を増やす。ジスキネジアを改善する。
- シンメトレル(アマンタジン)・・・インフルエンザの薬でもある。
抗コリン薬
ムスカリン受容体を抑制して、副交感神経を遮断し、パーキンソニズムを抑える薬。
パーキンソン病では、便秘が高率に発現するため抗コリン薬は使いづらい。そのため、抗精神病薬を投与している統合失調症患者の副作用予防に使われている印象。
- アーテン、トレミン(トリヘキシフェニジル)
- アキネトン(ピペリデン)
- パーキン(プロフェナミン)
- トリモール(ピロヘプチン)
- コリンホール(メチキセン)
- ペントナ(マザチコール)
NE前駆物質
ノルエピネフリンの前駆物質としてNEを補充できる。すくみ足にもちいる。
- ドプス(ドロキシドパ)
アデノシン受容体拮抗薬
アデノシンA2受容体の拮抗作用。
パーキンソン病では、間接路でGABAニューロンを抑制するために必要なドパミン量が低下し、GABAニューロンを興奮させるアデノシンの作用が相対的に高まるため運動機能が低下する。
A2A受容体拮抗薬はアデノシンの作用を弱めるkとによりドパミンとのバランスを保ち、スムーズな運動につなげることができる。レボドパによるウェアリングオフの症状を改善する。
- ノウリアスト(イストラデフィリン)
関連ページ
- パーキンソン病について
- ヘーンとレーン分類
- パーキンソン病の原因と症状
- パーキンソン病のメカニズム
- パーキンソン病の治療法・・・WearingOff、ジスキネジアの対処法
- レストレスレッグス症候群
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>